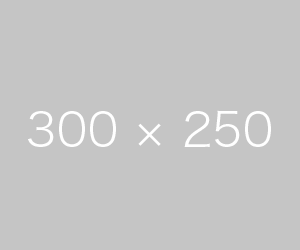認知行動療法
認知行動療法の考え方は、自分の認知(現実や起きた出来事の受け止め方)と、気分や感情と、行動や振る舞いとの関連がどうなっているかという観点から、心の不調や苦しみを理解するものです。
心の苦しみのありようは、「現実」や「出来事」を、私たちがどのように捉え、受け止めるか(「認知」あるいは「考え方」)、あるいは、そのうえで、どのように振る舞い行動するか(「行動」)に、大きく影響されています。
だから、ともかく、ものごとの捉え方や考え方を変えてみれば、それに伴って行動や振る舞いも、感情も変わります。
あるいは、ともかく、行動や振る舞いを変えてみれば、考え方も感情も変わり、どちらにしても心の苦しみが軽くなる可能性が高いのです。
そのためには、今の不幸せや心の苦しみが、自分のどんな考え方やどんな行動の習慣によるものなのかを、見つけてゆくことが大切になってきます。
つまり、私たちの幸不幸は、私たちの人生に何が起きたかで決定づけられるのではなく、それを私たちがどう受け止め、どう行動するかによるということです。ですから、「幸せ」に生きている人は、「幸せ」につながるような「受け止め方」と「行動」ができているということにほかなりません。
ものごとの捉え方、考え方を見直す
(認知へのアプローチ)
まずは、ものごとのとらえ方、考え方を見直すということからお話しします。
心の苦しみをこじらせてしまう典型的なものごとのとらえ方、考え方というのがあります。
「悲観的」、「否定的」な認知です。
例えば、ものごとが思った通りにいかないことは、誰にとってもよくあることです。
そんな時に、「自分はダメだ」とか、「ずっとうまくいかないことばかりだ」とか、
「誰も自分を助けてくれない」などと考えてしまう傾向、「癖」や「習慣」(これを「自動思考」と呼んだりします)が強いと、ますます自分を追い込んだり、苦しめたりしてしまいます。、悪循環的に不幸せに近づいていってしまいます。
そもそも、私たちは、不安だったり、心配ごとがあったり、ストレスが大きかったりすると、自然と悲観的で否定的な気持ちになりがちです。
人によっては、場合によっては、それをそのままに放っておくと、知らず知らずのうちにますます悲観的に、憂うつに感じやすくなっていきます。そうなると、日々の生活上の面倒ごとや、誰にでもある人生の否定的な側面などがたいそう重荷になり、行動が抑制されたり、行動できなくなってしまったりして、さらに不幸せ感が増して行きます。
「うつ」の人は、このような不幸せに引き寄せられていく「悪循環」のパターンが、慢性的になってしまっています。
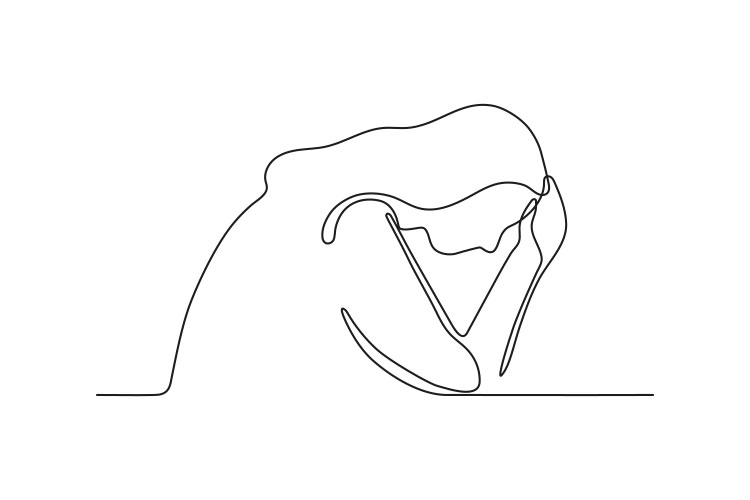
ですから、もし「悲観的」、「否定的」な受け止め方や考え方の「習慣」を変えることで、「悪循環」パターンから脱することができ、幸せに近づくことができるでしょう。
認知再構成
悲観的、否定的になりすぎる考え方の癖や、習慣を見直して、自分を暗い方向に進ませないようなものに修正する方法を、認知行動療法では「認知再構成法」と呼んだりします。
特に、自分にとってあまり良くない出来事が起きたときは、いつもの反応のパターンや悲観的な自動思考が出てきますから、認知再構成のチャンスでもあります。
その具体的な方法としては、「コラム法」がよく使われます。
例えば、なんでもよいのですが、良くない出来事の例として、「就職面接のあと不採用の通知が来た」としましょう。
まず、そのときの自分の嫌な気分がどんなもので、どの程度かを数値で判定してみます。
→例えば「焦り90%、絶望80%、不安70%」
さらに、そのときに頭に自然に浮かんでいる考えやイメージ(「自動思考」)と、それに対する自分の「確信度」も書き出します。
→「自分はダメな人間だ(90%)」、「この先も就職試験に受かる可能性は低い(80%)」、「就職できなかったら一生不幸に終わる(80%)」
これがまさに、自分の考え方の癖、パターンですから、そう考えてしまっている自分に、「果たして本当にそうだろうか」、「違う考え方はないだろうか」と問いかけ、疑問を投げかけてみるのです。
そう自問自答してみて、冷静に考えてみると、
「不採用になったのは単に会社との相性が良くなかったのかもしれない」、「そもそも採用される人数のほうが圧倒的に少ない」、「短時間の面接でそもそも人の能力や持ち味が判断できるものでもない」、「就職は運不運の要素もある」、「仮に今、就職できなかったところで、一生不幸になるわけじゃない」、「就職できたとしても、それで一生の幸せが保証されるわけではない」などの考えが出てくるかもしれません。
その一連の作業をやってみた後で、再度、嫌な気分の度合いを判定してみましょう。
→「焦り50%、絶望20%、不安50%」などというように、度合いが低くなっていることが多いと思います。
そうなると、再チャレンジをしてみようとか、何か別の進路や生き方を探そうとか、「行動」する意欲も沸いてくるでしょう。
厚生労働省HPには(一般向けの多くの認知行動療法の本にも)、以上の一連の作業を書き込める「コラム表」が掲載されていて、それに沿って自分で書き込み、取り組むことができます。
シンプルなやり方
認知行動療法のなかでも、以上のような「認知(考え方、受け止め方)」を見直して修正していく方法は、特に「うつ」に有効とされています。
ただし、自分の頭(考え)を使って自分の認知(考え方)を変える、自分の心を使って自分の心の癖を修正する、という作業は複雑と言えば複雑で、頭の中がごちゃごちゃしてしまって疲れてしまったり、理屈で考えすぎてしまい効果があがらなくなるということもしばしばあります。
ですから、もう少しシンプルなやり方も用意したいところです。
試しに、今の自分の現実がどうであろうと、とにかくおかまいなしに、自分を支え肯定する「ひとこと」を、繰り返し呪文のように口ずさんでみてください。
「私は素晴らしい」「私は大丈夫」、「私は幸せ」、「私は恵まれている」、「ありがとう」、「心配いらない」、「すべては幸せの種」とか、なんでもOKです。
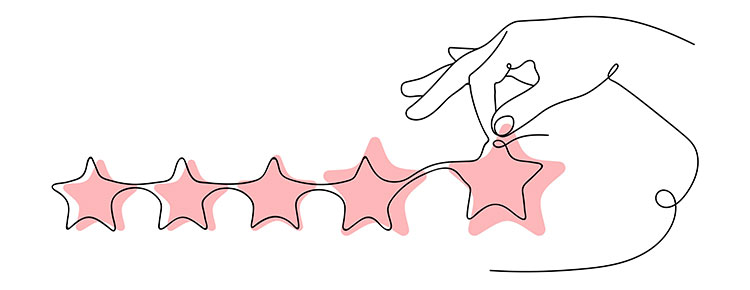
もし、「私は素晴らしい」と一日100回、一週間唱えてみたら、ほとんどの人が多かれ少なかれその効果を実感できるはずです。知らず知らずのうちに、脳がその言葉に沿ったものを見ようとするようになり、ものの見方や考え方が自然と変わってくるようになるのです。
不安や心配が高じたときだけでなく、気づいたときに繰り返し唱えてみてください。やってみれば100回なんてあっという間です。
実は私たちが、どんな「言葉」を選び、どんな「言葉」を使うかが、私たちの生きる「現実」をかたちづくっていくのです。
ただし、その際、すぐに気持ちが楽になったり、自分を受け入れられるようになることに、こだわらないでください。感情は自然物なので、自分から無理に変えることはできません。特に、否定的な感情や嫌な考えほど、意図的にコントロールするのは難しく、逆にそうしようとすればするほど、思うようになりません。
過去や現在の苦しみが強ければ強いほど、今の自分を肯定するような「言葉」を唱えることには、さまざまな抵抗が起こると思います。しかし、たとえどんな感情が湧いても、そこでどうするか、どう行動するかは、私たち一人ひとりが選べることです。
「言葉」遣いを含めて、自分を大切にするための具体的な行動やその習慣こそが、幸せに近づく一番の方法です。
「行動」してみる、「行動」を変えてみる
(行動へのアプローチ)
ですから、まずはあれこれ考えるのをやめて、何か「行動」してみる、「行動」を変えてみるということが思いのほか大切です。
「気分」や「感情」は変えられなくても、「考え」や「受け止め方」が変えづらくても、それでも「行動」を変えることは可能です。
先にもお話ししましたが、「行動」が変われば、「感情」や「気分」も変わり、「考え方」や「受けとめ方」も変わり、苦しみの「悪循環」が改善することが多いのです。
認知行動療法関連の書籍やサイトには、どんなときにどんな行動や振舞いをすれば、私たちの苦しみが軽くなり、幸せに近づけるのかという知見がたくさん集積されています。
後にいくつかを紹介しますが、例えば、楽しみを感じること、(ささやかな)達成感を感じられるようなこと、気晴らしになったり気が紛れたりすること、などはほとんどの人に効果がある行動です。
逆に、自分の悩みや苦しみを繰り返し考えることが、逆に苦悩を増し、メンタルヘルスには悪いというエビデンスもあります。これは、どちらかというと精神分析的なカウンセリングの考え方とは逆のスタンスですね。
いずれにせよ、心の健康を保てている人は、自然とそのような行動や振る舞いを通じて、自分を支えたり、困難を乗り切ったりしていることが多いのです。
日ごろからの準備の大切さ
ただし、苦しみが強いときには、逆に、気晴らしや、楽しみや、自分を癒すような行動は、なかなかできなくなってしまいがちです。追い込まれると、自分の得意なことが逆にできなくなってしまうこともあったりします。
ですから、日ごろから余裕のある時に、自分の人生で大切なこと、価値を置いていること、生涯を通じての目標などを書き留めておき、それに近づく小さな一歩としてすぐにでもできそうなことを、複数、箇条書きにしておくとか、自分がほっこりしたり、気持ちが和らいだりするようなことを、複数、リストアップしておきましょう。
それは自分で見つけるのが一番いいのですが、例えば、「HAPPINESS IS ~幸せを感じる500のこと(リサ・スウェーリングほか著 文響社)」をパラパラとめくると、何かしら試してみたいことに出会えるでしょう。その他、伊藤絵美著「セルフケアの道具箱(晶文社)」、「コーピングのやさしい教科書(金剛出版)」なども、読みやすくておすすめです。
ちなみに古代ギリシャ時代の心の養生法は、睡眠、入浴、良い食事、運動などです。きっと時代を超えて、私たちが普遍的に癒されることなのですね。
個人的なことですが、私は自分の心の苦しみを、体を動かす習慣(ジョギング・ランニングが主です)によってケアしてきました。落ち込んでいたり、自分の人生がままならないときも、外に出て走ればある程度は気持ちが持ち直し、活力がどうしようもないところまで落ちてしまうのを抑えられることが多いのです。
私は今まで、身体を動かし汗をかくことがストレス発散になるのだろうとか、そんなときに外に出て走るのは決して楽なことではないので、その頑張りが自分を立て直すのだろうなどと思っていたのですが、最近の脳科学の知見によって、運動の高い効用がいろいろ明らかにされていて、とても納得でした。
例えば、一日20分以上、週2~3日以上のジョギングやウォーキングなどの有酸素運動を習慣づけると、脳細胞の成長や脳内物質の分泌などを促し、不安やストレスが減る、集中力・やる気・意欲が高まる、行動コントロールが容易になる、記憶力・創造力・知能を高める、抑うつを改善する、脳の老化や認知症を防ぐ、などのエビデンスが明らかになっており、今のところ、運動以上に脳のそれらの改善効果を高める活動は見つかっていないそうです。
興味がある人は、「一流の頭脳(A.ハンセン著 御舩由美子訳 サンマーク出版)」、「脳を鍛えるには運動しかない(J.レイティ著 野中香方子訳 NHK出版)」などを読んでみてください。
自分のための行動レシピ
ただし、だからといって誰にでも運動が一番良い方法というわけではありません。私は小さいころから落ち着きがあまりなくて、よく身体を動かしていたので、きっと、運動が自分に合っていたのだと思います。
ですから、身体を動かすことよりも、もっと自分に合ったもの、向くものがある人も多いでしょう。
大切なのは、自分のために、自分に合ったもの、向いているものを見つけていくことです。
それは、一般的に評判が良いものとは限りません。人からみれば一笑に付されたり、価値がないと思われたりするようなことかもしれません。
できれば、自分の持って生まれた資質や、向き不向きに合っているものがいいと思います。幼い頃に自然とやっていたこととか、あるいは、心ひかれたけれど、どうせ成功しない食べてはいけないからと、見送ってきたり断念してしまったことなどに、そのヒントが隠されていることが多いようです。 いずれにしても、自分の感じるところに従って実際にやってみて、自分に合うものを見つけていく、そのトライ&エラーの営みは、間違いなくあなたの人生の豊かさにつながるはずです。
行動やその結果を記録してみる
そのほか、自分の行動の見直しや改善のために、随時、自分の行動やその結果を記録するという方法も効果的です。
認知行動療法では、「活動記録表」(これも厚生労働省HPに、具体的なサンプルが記載されています)を用いて、一日の行動記録を一定時間ごとに記入し、そのときの気分も合わせて、自分をモニタリングしてみることで、生活リズムを整えつつ、自分にとって良い行動、役に立つ行動を知り、それを増やしていくということを目指したりします。
このような「活動記録」や「活動日誌」をつけることで、うつや不安が軽減されたり、ダイエットや禁煙などの行動コントロールにも助けになるというエビデンスもあります。
詳細な活動記録が面倒な人は、おおざっぱなものでも、手帳へのメモ程度のものでも構いません。とにかく試してみることが肝心です。
先に紹介した「コラム法」もそうなのですが、このように紙に書きだして、記録してみることは、自分や自分の悩みや苦しみを、俯瞰的な視点から見ることにつながりますから、それだけでも価値があります。
自分の悩みや苦しみを、自分の外の視点から俯瞰して見ることは、悩みや苦しみが軽減する一つの秘訣だからです。
自分の行動をコントロールできるという実感
繰り返しになりますが、自分の苦しい気持ちや嫌な感情を変えようとか、なくそうなどと思い過ぎてしまうことが、かえって、私たちの苦悩を大きくしてしまいます。ですから、「行動」してみたからといって、すぐに「気分が晴れ」たり、「心が楽になること」を欲しがり過ぎないようにしましょう。
大切なのは、良くない気分を変えようとすることよりも、たとえ気分がどうあっても、自分の行動を、ある程度コントロールできるという実感が持てるようになることです。
特に調子がひどく落ち込んでいるときや、苦しみが長く続いているときには、日常生活のルーティーンそのものが思うままにならないことが多くなります。
だからこそ、生活のリズムをできるだけ整え、最低限の日常のルーティーンを淡々とこなすことこそが、心の苦しみや精神的不調からの回復にとても有効なのです。
嫌なことでもやってみる
その意味では、楽しいこと、気晴らしになりそうなことばかりでなく、嫌な気分が増しそうなことでも、あえてチャレンジしてみることも大切です。 私たちがこの世の中を、この社会を生きていくためには、それも必要なことです。
私たちは生きている限り、誰もが嫌なことや避けたいこと、怒りが沸くことや悲しいことに出くわします。そして、そんな苦しみはできるだけ感じたくないですから、嫌なことを避けようとする心の動きが起こります。
それはそれで自然で大事なことですので、要はバランスの問題ではあるのですが、私たちがこの世の中を、この社会を生きている限り、嫌なこと面倒なことを延々と避け続けようとしてしまうと、逆に、心の中のせめぎ合いが起こって、相当のエネルギーを消耗してしまうばかりか、直接の嫌なことだけに限らず、その他多くのことも含めて、自分の行動範囲や人生が狭まってしまい、結果的に心の苦しみや精神的な不調が長引いてしまうということが起こり得ます。
そもそも自分を守るために嫌なことを避けたはずなのに、それで余計、心の苦しみがこじれてしまい、幸せから遠ざかってしまうということがあるのです。
認知行動療法には、そうならないための方法も用意されています。
たとえば、「暴露」と呼ばれたりする方法は、嫌なことを避け続けたり、そこから逃げ続けたりするのをやめて、一度、覚悟を決めて我慢して向き合ってみる方法です。
そうしてみると、当然、一時的に不快感や怖さは増しますが、一定時間を過ぎると不快感や怖さが和らぎ、当初の嫌だった感情も軽減され、心の安らぎや狭めてしまった体験の回復に近づける可能性が高まります。
たとえるならば、「清水の舞台」から飛び降りる覚悟を決めたら、今まで思ってもみなかった世界が開けるといったところでしょうか。
その場合、思い切って一気に飛び降りてしまう(向き合う)とか、まずは低いところから飛び降りてみて、慣れたら段階的に高くする(徐々に向き合う)とか、緊張や恐怖感を和らげるために、深呼吸や何かの自己暗示を入れて、リラックスを心がけながらやってみるなど、いくつかのやりかたがあります。
行動を活性化する
関連して、「行動活性化」という考え方もあります。
私たちが生きていくためには、避けられない日常の「雑事」が山ほどあります。また、人生を自分なりに充実させたければ、そのためにやらなければならないこともたくさん出てきます。
しかし、心が苦しいと、それらのことがひどく面倒になってしまいます。そこで、気持ちが落ち込んでいるから、気分が晴れないからと、「雑事」ややるべきこと先延ばしにしてしまうと、そのこと自体が重荷になりがちですし、それを繰り返せば繰り返すほど、生活のリズムや意欲自体が損なわれて、逆に心の苦しみやうつ状態が長引いて、深刻化してしまいます。
ですから、たとえ気分や気持ちはどうであれ、とにかくそのままにしておいて、今すべきこと、できることをこなしていくという姿勢が肝心になるときも多いのです。
その意味では、心が苦しいときやうつ状態のときに、とにかく無理をせず休むのがよいというは一般的な常識ですが、そこに落とし穴があるケースもあったりするのです。
この「行動活性化」に関しては、「うつを克服するための行動活性化練習帳(ディアスほか著 大野裕ほか訳 創元社)」が分かりやすくて参考になります。
ただし、心が辛いとき、苦しいときに、休んだほうがいいのか、あるいは、行動を変えたり増やしたりした方がいいのかは、自分で判断するのが難しいときがあるかもしれません。そんなときは、もし信頼できそうな専門家が見つかれば、一緒に考えてもらうのがいいでしょう。