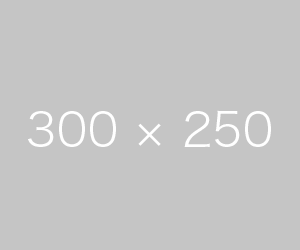認知行動療法の考え方のところでお話しした通り、自分の行動やものごとの受け止め方を変えてみればいいとはわかっていても、心の痛みや苦しみが大きいと、それに圧倒されてしまい、そこで多くのエネルギーを消耗してしまい、その余裕がなくなってしまいます。
そんなとき、「マインドフルネス(瞑想)」と呼ばれる実践や習慣を通して、心の痛みや苦しみに人生を左右されないようにする、心の中の戦いを減らして本来のいのちのエネルギーを回復する、という方法があります。
この「マインドフルネス」に関しては、今やポピュラーな心の回復法として、さまざまな関連書やインターネットのサイトや動画が出ています。おすすめは、ティク・ナットハンという人のもので、「ティク・ナットハンの幸せの瞑想(徳間書店)」や「プラムビレッジ(Plum Village)」HPなどです。
それらを見てもらうのが一番いいのですが、ここでも簡単に説明しておきましょう。
今この瞬間を大切に生きる
「マインドフルネス」とは、「今この瞬間」の自分や体験に、価値判断を行わず、しっかりと気づき、生きる姿勢です。
それは、自分や周囲に対してのこだわりから自由になり、ものごとのあるがままのありようや、森羅万象の「無常(移り変わり)」を受け容れる生き方の体現です。
「マインドフルネス(瞑想)」の実践を通じて、「今この瞬間」こそに存在する「癒し」と「幸せ」にアクセスすることができ、その結果、ストレスの低減、不安や抑うつの改善、感情調整力・幸福感・集中力の向上、心身の健康の増進、さらには、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の影響や生物学的な要因などによる脳の脆弱ささえも改善されうるとされています。
辛い心の痛みや苦しみに自分の人生を左右されないようにする、そのためのとても力強い味方がマインドフルネス(瞑想)です。
心の苦悩のほとんどは、「今ここ」の瞬間から心が離れ、嫌な「過去」を想い出したり、不安な「未来」を心配したりすることから成り立っています。
でも、現在のまさに「この瞬間」には、実は「不安」も「恐れ」も存在しません。
だから、「今ここ」のひとときひとときを、確かに生きることができるようになればなるほど、苦悩から自由になることができます。
私たちの日常はその逆で、ご飯を食べながら過去の失敗を悔やんだり、顔を洗いながら将来のことを気にかけるなど、常に心がさまよっています。
過去や未来にとらわれがちな心を現在に戻してあげて、「今この瞬間」と共にいることができれば、そのこと自体が「癒し」であり「幸せ」の一つのありようなのです。
マインドフルネスの実践を続けていけば、今この瞬間を味わい、生きる習慣が暮らしの中に馴染んでいきます。
そして、何か達成をすることや、優れた業績を成し遂げることや、経済的に豊かになることなどとは、違った次元に存在する「幸せ」に開かれていくでしょう。
心の苦しみを終わりに導く方法
それもそのはず、「マインドフルネス」は、ブッダによる「心の苦しみを終わりに導く方法」です。
すべてのものが移り変わる「無常」のなかで、今この瞬間の自分と共にいること。
自分の心の中で起こる欲望、怒り、淋しさ、迷いなどの「執着」が沸き上がり、そして去ってゆくさまを、俯瞰する視点から思いやりを持って見てあげること。
そのためには常に自分と共にある「呼吸」を拠りどころにすること。
ブッタの「呼吸を通じた『16の練習』」を通じて、私たちはこれまでの苦悩から解放されるばかりか、怒りや嫌悪や孤独や苦悩を生じさせ、かつ、それらを抑えこむためにも要していた莫大なエネルギーが、逆に価値のあるエネルギーに変容して、私たちのいのちに満ちた、生き生きとした日々を回復してくれるのです。
参考までに、「呼吸による癒し(ローゼンバーグ著 井上ウィマラ訳 春秋社)」は、以上のことを、自らの体験を踏まえて、とてもきちんと解説してくれています。
マインドフルネスの実践法
具体的な練習方法についても簡単にお話ししておきましょう。
例えば、「マインドフルな呼吸」の練習は、まさに「今この瞬間」の体験である呼吸に意識的な気づきを向ける取り組みです。
自然な呼吸を続けながら、鼻や口に息が出たり入ったりする感覚や、お腹が膨らんでくる感じやへこんでいく感じなどに意識的に注意を向けます。
その間、意識が呼吸から逸れることがあるでしょう。それに気づいたら、それを(とがめずに)受け入れてあげて、穏やかに注意を呼吸に戻すということを繰り返します。
それに馴染んできたら、さらに、「今ここ」の気づきを向ける対象を、他の身体の感覚、自分の中に沸く思考や感情に、飲んだり食べたりしているときにはその感触や味に、歩いているときにはその一歩一歩に、皿洗いをしているときにはお皿や流れる水の感覚そのものに、などなど、生活上の具体的体験に広げていきます。
つまり、日常生活のほとんどの営みが、「今ここ」の体験や感覚に集中することによって、マインドフルネスの実践練習になるのです。
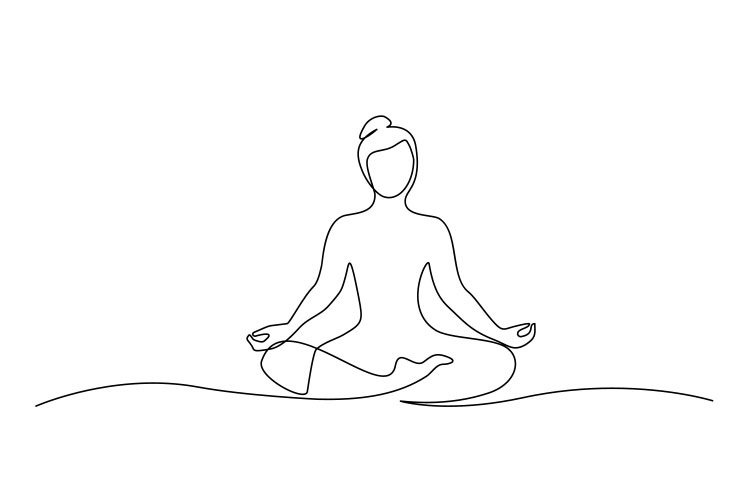
ただし、練習の際、一番扱いに困るのは、自分の心そのものが生み出す思考や感情です。
特に、不安や怖れや怒りや嫌悪などいわゆる否定的な感情です。
それらが起きたときには、それらについてことさら考えたり、良し悪しを判断したり、抑え込もうとか、戦ったりせずに(つまり、執着せずに)、「考え」が浮かんでいるな、とか、「不安」が起こっているななどと、自分とそれらの対象との「間」を保って、俯瞰した視点から見てあげるのが、かんどころです。
それらに、「不安(が浮かんでいる)」「悲しみ(が湧いている)」「怒り(がある)」「判断・批判(をしている)」などと、シンプルな言葉をつけてみたり、空に浮かぶ雲や、川面を流れる落ち葉にそれらを乗せて、自然に流れてゆくイメージを描いてみたりすることも、「距離」を取ってあるがままに眺めることを助けてくれるでしょう。
どんな「考え」や「感情」も、自然に湧いてきて、自然に去っていきます。
それは雨や風と同じで、どんなに嫌で苦しい感情であっても、そのまま永続するということはあり得ません。
それらと戦い、それらを抑え込もうとすればするほど、かえってそれらの「ダークフォース」が長らえてしまいます。
桜の花が自然と咲いて、時期が来れば自然と散っていくように、それらの感情や考えが自然に開花し、自然に散ってゆくのに任せる、それが、こころの苦しみに人生を支配されず、心の平静を保つ大きなかんどころです。
マインドフルネスを取り入れたカウンセリング・心理療法
「マインドフルネス」、つまり、ブッダの「心の苦しみを終わりに導く方法」は、今や、ヨーガなどの心身健康法や、さまざまな感情調整や行動変容の方法、さらには、これまでにお話しした来談者中心療法や精神分析的カウンセリングの考え方なども取り込んだ、種々の統合的なカウンセリング・心理療法へと発展してきています。
そのうち、皆さんが本を読んで、自分で試せるようなもののいくつかを、以下に紹介しておきます。なかには、自ら強い心の苦しみを抱えてきた著者が、それをなんとかしようとして考え抜いた方法もあり、特に、長らく心の苦しみを抱えている人は、いずれも読んでみる価値ありです。
マインドフルネスストレス低減法
ボブ・スタールほか著 家接哲次訳 「マインドフルネスストレス低減法ワークブック」 金剛出版
アクセプタンス・コミットメント・セラピー(ACT)
S.ヘイズほか著 武藤崇ほか訳 「ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)をはじめる セルフヘルプのためのワークブック」星和書店
弁証法的行動療法(DBT)
S.スプラドリン著 斎藤富由紀監訳 「弁証法的行動療法ワークブック あなたの情動をコントロールするために」金剛出版
コンパッション・セラピー
T.ディズモンド著 中島美鈴訳「セルフ・コンパッションのやさしい実践ワークブック」 星和書店
マインドフルネスの癒し
私たちは、たとえどんな「苦しみ」や「困難」を抱えていたとしても、「今この瞬間」に十分に開かれ、この瞬間を生きようとすることで、心の平安を回復し、豊かで幸せな人生に近づくことができるのです。
そうやって、私たち一人ひとりが、自分の不安や苦悩、あるいは、怒りや不機嫌などにうまく対応できるようになって、心の平穏を取り戻し、自分を慈しめるようになると、
それは、他者への思いやり、人々の共存・共栄、世界平和、ひいてはすべての生きとし生けるものへの慈愛につながっていきます。
なぜなら、個人や家族内に起こる苦しみやいさかいはもちろん、政治や経済活動、国や民族同士の対立に至るまで、この世の中のほとんどの出来事は、人々の感情や機嫌で動いているからです。
「マインドフルな歩みとマインドフルな呼吸のひとつひとつは、今ここの瞬間に平安をもたらし、戦争をなくすことにつながる。もし、私たちひとりひとりの意識が変わったら、人類全体の意識を変えるだろう」 (ティク・ナットハン)