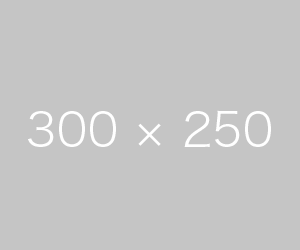「精神分析」の考え方
「精神分析」はS.フロイトという人が考え出した、心の苦しみのとらえ方やその治療の仕方の仮説セットです。先にお話ししたロジャーズの考え方とは、かなり異なりますが、これも、私たちの心の苦悩のからくりを理解し、そこから自由になるためにとても役立つ考え方です。
心の中のエネルギー
その一番の特徴は、私たちの心の中には、いわゆる「無意識」とか「潜在意識」とか呼ばれる自分ではなかなか気づけない力が存在して、いわば「ダークフォース」的なエネルギーを持ち、私たちの人生に少なからずの「影響」を及ぼしているというものです。
そのうち典型的なものとしては、例えば、辛い体験、怖かった体験、ひどく心細かった体験、深く傷ついた体験や、その際に自分がどう反応して、どう危機を脱しようとしたかといった経験は、良くも悪くも重要な学習記憶として心の中にインプットされます。
再び同じような危機が起こったときに備えて、その時の「嫌」で「危険」な状況や雰囲気とともに、ほかならぬ自分がどう反応したか、どう危機を逃れようとしたか、という対処や振る舞いの記憶や学習が、私たちの意識を超えて心の奥底に蓄積されています。
この自分が脅かされるような体験から自分を守って、乗り越えようとする心の働きは、生まれながらに誰にでも備わっている「いのちの働き」ですが、その対処のパターンやそれがどう発動するかにはバリエーションがあります。
ときに、私たちが日々の生活上、何らかの「危険」を嗅ぎ取ったり、感じたりすると、その対処パターンが意識の制御を超えて発動してしまうことがあり、そのことがより自分を苦しめ、安らかに生きられないという現象がしばしば起こります。その対処パターンが、もはや現在の状況や周囲との関係にはあまり馴染まなくなっているからです。
「トラウマ」とか「心的外傷」とか呼ばれるものは、その典型例です。そして、それが小さい頃の体験であればあるほど、強ければ強いほど、繰り返されればされるほど、自分の人格に組み込まれますから、自分の中の「ダークフォース」の力が強くなり、生活上に大きな影響を及ぼします。
いずれにせよ、今の自分の苦しみや生きづらさには、深いレベルで学習された対処のパターンが悪影響を及ぼしていると考え、カウンセラーとともに過去のことを十分に振り返ったり、例によっていつもの対処パターンが出てきたときに、よく話し合うことで、そのからくりを見抜き、もう少し役に立つ新たな対処パターンを身につけていくのが、精神分析的な支援の特徴ということになります。
よくある対処のパターン
私たちの対処パターンのうち、よくあるバリエーションは、「防衛機制」として整理されていたりします。文字通り「不快で受け入れがたい感情(や欲求)から自分自身を防衛するための心の機能」ですが、そもそも自分を守るための「対処パターン」を過度に、あるいは、不適切に発動させてしまうことによって、逆に苦しみや不調を余計にこじらせて、不幸せになってしまうことがあるという視点が大切です。
よくある対処パターン「抑圧」「否認」
嫌な経験や苦しい感情を心の押し込めて感じないようにする、忘れようとする、なかったことするという心の機制は、「抑圧」や「否認」などと呼ばれます。
現実に我が身に起こったことのつらさ、苦しさ、淋しさ、怒りなどなど、受け入れがたいものを見ないように、感じないようにして、何とか乗り越えようとする心の働きです。
でも、一度起きたこと、体験してしまったことは、なかったことにはなりません。そうした体験記憶は、心の奥底に閉じ込めたとしても、「ダークフォース」として、ことあるごとに私たちを苦しめることが往々にしてあります。
例えば、漠然とした不安や心配がなかなか晴れることがなかったり、理由もなく苛立ちや不機嫌が続いたり、日々の生活に意欲や希望がなかなか持てなかったり、対人関係や家族関係で同じような苦しみが繰り返されたり、不意に嫌な体験や感情が沸きあがってきたりなど、さまざまな出現のしかたをします。
典型的なのが「フラッシュバック」と呼ばれるものです。「フラッシュバック」には、比較的深刻なものも、そうでもないものもありますが、嫌で避けたい生々しい感情や苦しみの体験が、自分の意志を超えて引き起こされる現象です。
これは、決して異常な心理ではなく、嫌なこと辛いことが起こったあとの私たちの自然な反応ですが、それが数か月や年単位で長引いてしまったり、ごく些細な刺激に過敏に反応してしまったり(「過覚醒」)、その一方で、逆に刺激への反応が鈍くなったり(「感情鈍麻」)、記憶や意識の連続性や一貫性がなくなったり(「解離」)、それらの混乱が併発したりすると、いわゆる「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」として、治療の対象になることがあります。

よくある対処パターン「行動化」
心の奥に押し込めた感情や、抑圧された欲求や葛藤、我慢やストレスなどが、自分では制御しがたい「行動」や「言動」として顕在化することがあります。
いわゆる子どもの「問題行動」の多くはこれですし、私たちも「ストレス」が高じると、物に当たるとか壊すとか、ほかの人に当たるとか、悪口陰口を言うとか、怒鳴ったり叫んだりとか、貧乏ゆすりが激しくなるとか、余計に食べたり飲んだりしてしまうとか、性的刺激などの快楽を求めたり、それに執着したりなどの「行動」で、心のバランスを取ろうとします。
また、強いストレスという意味では、先の「フラッシュバック」様の体験が繰り返されている場合にも、それに対抗するために「行動化」が起こります。
それらの行動が極端になったり、続いてしまったりすると、他者への暴力や自傷、過食や拒食、浪費、盗癖、アルコールや薬物への耽溺、過度な性的な振る舞いなどの習慣的パターンが形成されてしまい、専門的な支援の必要性が高まります。
よくある対処パターン「身体化」
同じように、嫌なことや受け入れがたいことを押し込め続けていると、心の中の「ダークフォース」が力を持ち、「からだ」に悪さをしてくることがあります。
例えば、発熱、頭痛、腹痛、歯痛、腰痛、手足のしびれ、耳が聞こえづらくなる、目が見えづらくなる、字が書きづらくなる、話しづらくなる、歩きづらくなるなどですが、「心」の不調としてではなく「身体」の不調や病気として顕れるものです。それらの症状は、身体の病気の治療だけでは、あまり良くならないことが多いです。
よくある対処パターン「投影」
自分自身の中にある嫌な気持ちや不快な感情、受け入れがたい感情を、相手が持っていると思い込むことで、自分の本当の苦しみを見ないですむようにするパターンです。
例えば、自分に苛立ちや怒りがあり、それを心の中にとどめていると、身近な人に対して、それを映し出すかのように、「怒っている」とか「不機嫌」だなどと相手を責めてしまうようなものが典型的です。
あるいは、自分の不安や苦しみを自分で引き受けられないがために、他の人のせいだと思い込み、相手を八つ当たり的に責めたり、法外な抗議をしてしまうこともあります。
それが極端になると、いわゆる被害妄想や妄想症(パラノイア)と呼ばれるような様相になり、自分をも相手をもひどく追い込んでしまい、不幸せになっていってしまいます。
自分の苦しみを自分で受け止められず、「誰かのせいで自分が被害にあって苦しめられている」と思わないとやっていられない無意識の心理です。
よくある対処パターン「退行」
辛いとき、苦しいときに、「子ども還り」して、幼いころの甘えや依存の雰囲気や、「わがまま(我が儘)」や「伸びやかさ」の状態に還って自分を守る、立て直すという対処パターンです。
「退行」は、周りからすると厄介なこともありますが、「自分を守る」ためのいのちの働きの健全な発現であることが多く、この「退行」がうまく使える人は健康な人でもあります。
よくある対処パターン「不安」や「うつ状態」
「不安」や「うつ状態」もその多くが、私たちが自分を守るための意識を超えた対処パターンです。
「不安」になるのは、この先、あまり良くないこと、受け入れがたいことが起こるかもしれないという予測、あらかじめの備え、対処ですので、「不安」があることによって、私たちの毎日は必要な行動に導かれ、さまざまな形で守られています。
ただし、それが過度になってしまうと、それ自体が辛いがあまりに「不安」を避けたり、なくしたりすることが日々の目標になってしまい、「不安」を生じさせるような場面や営みをできるだけ避けようとして、通常の生活や社会参加が困難になってしまいます。
「うつ状態」は、心やいのちのエネルギーが低下しているときに、気力や活力を落として、いわば「省エネ」状態で乗り切ろうとする対処法です。「死にたい」という気持ちが伴う場合もありますが、これもエネルギーの乏しさゆえ、すべてから解放されて「楽になりたい」という想いの顕れで、決して異常な心理ではありません。
基本的には、それらの声に従い、エネルギーがある程度回復するまで休むことや、「省エネ」で日常をこなすことが、対応の第一選択肢になるでしょう。
長引くこころの不調のからくり
以上の「対処パターン」は例外なく、もともとの辛さや苦しさから自分を守ろうとする心やいのちの働きと、その無意識的な学習体験の産物によるものです。
でも、それがその場を乗り切るのには役立っても、長期的、根本的な解決や癒しには結びつかないことが往々にしてあります。にもかかわらず、その「対処パターン」にこだわってしまうことで、逆に苦しみや不調を余計にこじらせ、結果として、自分の人生がより制限されたり、周囲との関係が悪化してしまうなど、不幸感が増していってしまうことがあります。
その一連のプロセスは、なかなか自分には見えにくく、自分では変えにくいので、専門家の助けが必要であるというのが精神分析的な考え方です。
心の回復のためには
そのためには、そのような「からくり」を見抜くことが大切です。
先のたとえで言えば、心のなかの「ダークフォース」は何度も何度も、同じようなパターンの「悪さ」をしかけてくるので、同じような人生上の苦しみや、うまくいかない人間関係が続いていれば、その「正体」と「からくり」に気づくチャンスです。
いったん、その「正体」と「からくり」を見抜けば、おのずからその影響力が減ってきて、今度は、それとは違う新たな体験や対処のパターンを増やしていけます。
例えば、似たような対人関係上の苦しみや困難が、相手を変え場所を変え、繰り返し起こるような場合とか、今の苦しみや不幸せに、過去のできごと、とりわけ子どもの頃の親との関係が影響していそうな場合などは、精神分析的な考え方が役に立つでしょう。
専門家カウンセラーの伴走の大切さ
この考え方は、自分の「意識」や理性的な部分を拠り所として、自分で自分の内面を見つめて探求したり、「分析」したりすることが得意な人に向いています。
でも、私たちの中には、本来、そもそも嫌なこと、苦しいことは見るのも聞くのも嫌という「分身」もいるので、なかなか難しい作業なのです。
その「分身」と敵対するのではなく、思いやりながら、でも、自分の苦しみや不幸のからくりを冷静に探って、新たなバージョンの対応を見つけていこうとする「わたし」を育てる必要があります。
だからこそ、共感的でありながら、かつ冷静な観点を兼ね備える専門家カウンセラーの伴走や、比較的長い年月の治療が必要とされることが多いのです。
ただし、それは専門家カウンセラーにとっても、それほどたやすいことではありません。強い苦しみを抱えた人は、カウンセラーに対しても「ダークフォース」による拗れやすいパターンを使ってきますので、それにうまく対応できないとなりません。
その意味でも、カウンセリングを受ける側もそれなりの覚悟が必要で、カウンセラーとの相性も大切ですから、カウンセラーの考え方や目指す目標、そのための方法や期間の目安などを十分に確認して、よく説明してもらってください。
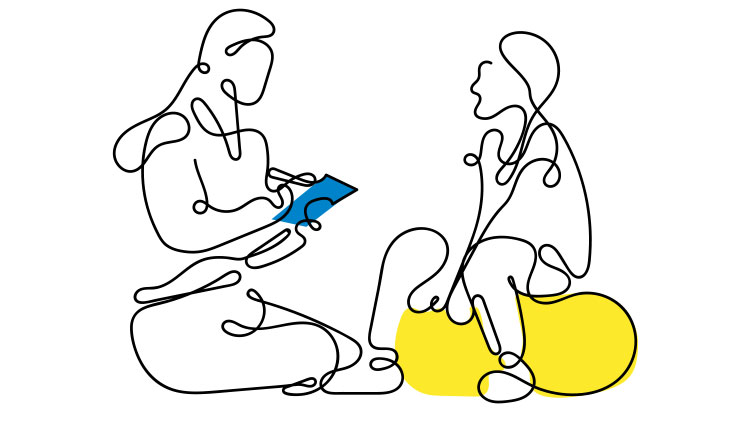
精神分析的な考え方を拠り所にカウンセリングを行う専門家は少なくありませんが、そのような説明やクライエントの納得を重視している人は、それほど多くはないように思います。
なんとなくカウンセリングを受けて、知らず知らずこの考え方に進まされていた、それが長年続いていたというのは、あまりいい結果にならないことが多いです。
カウンセリングを受けることで余計、不幸せになってしまっては本末転倒です。
「トラウマ」のストーリーの功罪
精神分析的な考え方は、今の不幸や苦しみが過去の体験に由来するというストーリーに私たちをいざないます。そのストーリーはとにもかくにも事態を落ち着かせてくれます。
特に、過去の「トラウマ」的体験を今の不幸の理由にするストーリーは、自分や他の人に対してわかりやすく強い説明力を持ちます。
それだけに、その見方やストーリーにこだわって、トラウマを負わされた「被害感」を主役に据えて、例えば、親や配偶者に苦しめられたことを責め続けて、その後の人生を生きていってしまうということもよく起こります。
実際、「トラウマ」と言われることの多くは、さまざまな要因が複雑に絡んでいて、何がその原因かは断定できないことが多いのです。
しかし、ときに専門家さえもが、そのストーリーの説明力に巻き込まれ、クライエントの被害意識やそれゆえの自分の人生の責任の棚上げを強めてしまうこともあります。同じく、カウンセリングを長期間続けても不幸感が一向に回復しない典型例です。
たとえ何があろうと、自分の人生は自分で引き受けるという姿勢を放棄してしまっては、私たちは決して幸せには生きられません。
頭の中で作り上げた「分析的」ストーリーによって、かえって、苦しみの実像や本質から離れていってしまい、「幸せ」から遠ざかってしまうということもあるのです。
カウンセリングを受ければ、ほとんどの苦しみが軽くなって、幸せになれると思っている人が多いかもしれませんが、それは間違いです。
それぞれの事情を背負ったそれぞれの人生には、喜びや楽しみだけでなく、純粋な苦しみや悲しみも含まれています。その純粋な苦しみや悲しみはカウンセリングによってなくなりませんし、なくそうとしてはいけません。
過去の苦しみに手を差し伸べる
過去の辛かった体験が今の自分を苦しめているのであれば、自分でその過去の苦しみを手当することも可能です。
例えば、一つの方法として、自分の中に、未だに傷ついていたり、苦しんでいたり、不安だったり、脅えたりしている「幼い自分」がいるとイメージして、今の自分がその子の面倒を見てあげてみてください。
今の苦しみは、その子が未だに泣いていたり、淋しがっていたり、怒っていたりして、助けを求めてきている顕れです。だから、無視したり、どこかに閉じ込めようとしたり、嫌ったりするのではなく、優しく寄り添って、頭をなでてあげたり、抱きしめてあげたり、しっかり手をつないであげて、その子の苦しみや悲しみをあなたが自らケアしてあげてください。
もし実際にどこかで、小さな子どもがひとりぼっちで泣いていたり、何かに脅えて怖がっていたとしたら、きっとあなたはその子に寄り添って、そうしてあげるでしょう。
是非、その子と一緒に素敵な花や美しい景色を見たり、一緒に美味しいものを食べたり、一緒に何かを楽しんだりしてあげてください。
もしかして、今の苦しみがとても強くて、そうしてあげることが難しいときがあるかもしれません。
そんなときは、辛く苦しい今の自分が、不安や怖さに脅えている小さな子どもと手をつなぎ、もっとおおいなる存在が、自分とその子のユニットごと抱えてくれているイメージを持ってみましょう。
傷ついた小さい自分を何とか助けようと頑張ってきて疲れ果てている自分をも、マリアさまとか、観音さまとか、お月さまとか、天国の安らぎとか、宇宙の深淵とか、何か超越した存在が見守ってくれていて、抱えてくれているイメージなどがきっと助けとなるでしょう。
たとえ毎回うまくできなくても、段々と自然にそれができるようになってきて、ときに、心の奥深いところから涙があふれてきたり、静けさの中で、かけがえのない自分へのいとおしさや、ほかでもない自分らしさとの出会いが訪れたりするかもしれません。
そんな瞬間は、きっと生涯にわたって自分を支えてくれるでしょう。
小さい頃から、辛いことが多かった人ほど、自分で自分が癒せるということがなかなか信じられません。でも、そうしようと決意し、あきらめず、練習すれば、自分で自分を癒すとことができるようになるのです。
というよりも、私たちは根本的には自分のことは自分で癒すしかないのです。
身近な誰かやカウンセラーは、それを見守ったり、手助けしてくれるだけの話です。