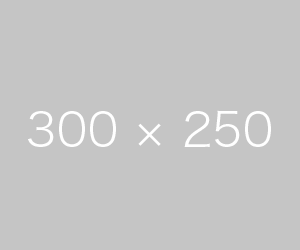あるがままの自分を受け入れる
私たちが心穏やかに、幸せに生きてゆくために欠かせないことは、「今のあるがままのそのままの自分を、自分自身が受け入れて、大切にできること」です。
私たちは誰もが、理想的な自分を生きているわけではなく、不十分な面をたくさん抱えています。もし、もっと容姿や体形が優れていたらとか、もっといい学校やいい仕事だったらとか、もっと明るく社交的な性格だったらなどと思いがちです。
だから、多くの人はなんとかしよう、もっと自分を良くしよう、努力して自分を変えよう、と頑張ります。
しかし、その考えが逆に自分を追い詰めてしまい、かえって幸せから遠ざかってしまっている人がとても多いのです。なかには、自分のダメさ、変わらなさに落ち込んだり、やる気や意欲を失ったり、毎日をふさぎ込んで過ごしている人もいます。カウンセリングに来る人たちの多くは、そんな苦しみを抱えています。
でも実は、自分を受け入れ、自分を大切にできるためには、今より優れた自分である必要はまったくありません。
たとえ、人と比べてどんなに劣ったところがあっても、自分のありようを受け入れて、かけがえのない「今」の、ひとときひとときを大切に生きようする人の人生は幸せです。
あるがままの自分、所与の持ち味を大切にして生きようとすると、そこに希望や意欲や夢が湧いてきます。
一方で、どんなに人がうらやむような地位や境遇にあっても、もっと優れた人やもっと幸せそうな人と比較して、自分をさいなんでしまうような人もいます。どんなに能力が高くても、どんなに頑張って自分を高めたとしても、今の自分を受け入れることができなければ、結局は心穏やかに暮らしていくことはできません。
来談者中心療法の創始者 C.ロジャーズの考え方
カウンセリングの父とも称され、カウンセラーを志す人が必ずその理論を学ぶ、カール・ロジャーズという人は、私たちがあるがままの自分を認めて、ありのままの体験や感情を受け入れられるようになることが、幸せへの道だと考えました。
私たちは何かができるから、何かをしている(doing)から価値がある(=条件付きの肯定)のではなく、ただ、あるがままの自分として存在する(being)ことこそに価値がある。だから、私たちが今の自分を嫌わず、自分の感情や体験を信頼して、尊重できるようになれば、幸せな生き方に近づけると考えたのです。
でも、あるがままの自分を受け入れるのは、口で言うほど簡単なことではありません。だからこそ、多くの人が、現実の自分と、こうあるべき、こうありたいと思っている自分とのギャップに思い悩んだり、苦しんだりしているのですね。
無条件の幸せのありよう
とりわけ、わが国には、今の自分や自分が置かれている現実が嫌でたまらず、「死にたい」と思っている人たちがたくさんいます。実は、日本の自殺率は世界屈指で、特に若い人たちの自殺率が極めて高い国です。経済的に豊かで、しかも、さし迫った戦争やテロ、民族紛争などの脅威もほとんどない平和な国にもかかわらず、数多くの日本人が不幸感にさいなまれているのです。
でも考えてみれば、そもそも自分が嫌だとか、自分が劣っているとか、世の中に存在してはいけないんだと思って生まれてくる子どもは誰一人としていません。
人間だけでなく、生まれたての子牛が自ら立ち上がろうとし、孵化した蝶が空を舞い、小犬があたりを駆け回るように、すべての生きものが、生来の資質に応じて伸びやかに生きようとします。それはとりもなおさず、この世に生を受けた生きものの、私たちの、無条件の幸せのありようにほかならないと思います。
私たちは誰もが、この世に無条件に存在する(being)価値を生来的に持ち、多くの場合、ものごころがつく頃までは、自分のbeingを伸びやかに生きています。
ロジャーズは、そんな小さな子どもの頃の、内発的な好奇心や好き嫌いの感情に基づく「価値」、つまり、本来の生命力に根ざした経験の選択(=「価値づけ」)を最大限に信頼したのです。
価値の条件による苦しみ
しかし、私たちは、その後の成長に伴って、親や、自分にとって大切な人や、集団からの愛情や承認を求めるがゆえに、周囲から評価されるような「価値」基準に基づいて、「優れた」人になることを目指すようになっていきます。それがすなわち「幸せ」と同義になり、その意味での「安心」や「幸せ」に少しでも近づくために、我慢や努力を重ねて、生来の伸びやかさや、生来の「価値づけ」を抑えるようになっていきます。
ロジャーズはこれを、「価値の条件(=条件付けされた価値づけ)」の悪い影響とみなしました。
私たちが、今の自分の不十分さや足りないところばかりが見えてしまうのは、そんな「価値の条件」に沿った優劣や所有の程度を、「幸せ」の基準にする習性が染みついてしまっているからです。
容姿、顔立ち、体型、学力、運動能力、絵や音楽の能力、社交性、仕事や職種、その他、他人との比較の中で優越感や不安が煽られます。つまり、人との比較や優劣が、私たちの努力や頑張りを動機づけ、その意味での「幸せ」を達成したいという思いを強く刺激するのが、良くも悪くも現代社会の基本的なあり方です。
その習性は、私たちの身近な日常生活にしのび込んでいます。
親は、もし子どもが言うことをよく聞けば、テストの点が良ければ、いい学校に合格すれば、サッカーで試合に勝てば、難しい曲が弾けるようになれば、機嫌よく子どもに接するけれど、思うような成果が挙がらないと、頻繁にダメ出しをしたり、叱ったり、そうではなくとも、不機嫌になったり、がっかりしたような雰囲気になってしまうことで、子どもは、「自分ができないのがいけないんだ」、「自分が悪いんだ」という気持ちになりがちです。
もし、そんなことがずっと繰り返されたとしたら、子どもは「今の自分のままでは価値がない」、「もっと頑張らないと認めてもらえない」、「もっと優れた存在でないと愛されない」という思いを募らせていきます。
子どもの社会へのかかわり方は、親子関係がベースとなります。だから、そんな子どもたちは、学校や社会に出ても、何かができなかったり、人より劣っていたりすると、自分は受け入れてもらえない、存在する価値がない、などと自分をさいなんでしまうようになりがちです。
学歴が髙くないと、格好が良くないと、何かで成功しないと、周囲から認められない、幸せになれない、だから、嫌なこと、辛いことに耐えて頑張らなくてはならない、一生懸命努力しなくてはならない、といった後付けで学習された条件付けや信念が、視野を狭め、自分をどんどん追い詰めます。
ときに、その前提条件は根深い「こだわり」や「執着」となって、自分のいのちを損なってしまうような強力なものにさえなるのです。
そんな繰り返し学習されてきた「価値の条件」に気づき、それを緩めない限り、今のあるがままの自分を受け容れようといっても、無理なことです。
よく注意してみると、社会的に高い地位にある人が不機嫌で、憂うつな毎日を過ごしていたり、周りの身近な人たちがひどく苦しめられていたりすることが少なくありません。運動でも、芸術や芸能の分野でも何でも、その道で名を遂げた人とて、心穏やかでなかったり、不安や怖れに苦しんでいる人たちがたくさんいます。
どんなに成功して、どんなに有名になっても、今の自分を受け入れられないと、私たちは不幸せです。
自己実現
その意味では、自分が確信する幸せの前提条件は、自分の幸せを決定づける唯一の道ではありません。
逆に、よく見てみると、社会的な価値観上、いわば「幸せの既定路線」に乗っていないような人たち、普通で「平凡」と思われるような人たちの中に、日々を幸せに暮らしている人が多くいます。
その人たちにも、もっとこうなりたいという想いはあるのでしょうが、今の自分の置かれた状況で、自分の限界を受け入れて、やれること、やるべきことをこなしながら、日々の恵みに感謝して、人に助けてもらったり、人に貢献してあげたりして、生き生きと暮している人たちが少なからずいらっしゃいます。実は私たちが生きるこの世界の平和の大部分は、そういう人たちのおかげで成り立っています。
ロジャーズ自身も、そんな親からの条件付けの「愛情」に苦しんだ一人です。その経験をもとに、私たち人間には、生まれながらに自然な自己実現傾向、すなわち、自分の体験や感情に即して生き生きと、幸せに生きられる力が備わっているはずなのに、親のかかわりが条件付きであればあるほど、子どもは「親が気に入るように行動しなければならない」という思いが強くなり、自分らしさや自然な自己実現傾向を抑え込んでしまう。心苦しむクライエントはまさにそのことに苦しんでいる人たちだ、と考えました。
そして、それが癒されるためには、親や社会の「価値の条件」にかなわなくとも、自分本来の自然な感情や体験に開かれ、それを行動や幸せの指針として信頼できるようになり、
そんなあるがままの自分を受け入れ、生きていくことがとても大切で、それこそが本来の自己実現だと考えたのです。
人と人との出会い
そのために大きな助けとなるのが、人との出会いです。今の自分のありようがたとえどうであったとしても、そんなあなたのことをそのまま受け止めてくれて、共感してくれて、大切にしてくれる人との出会いです。
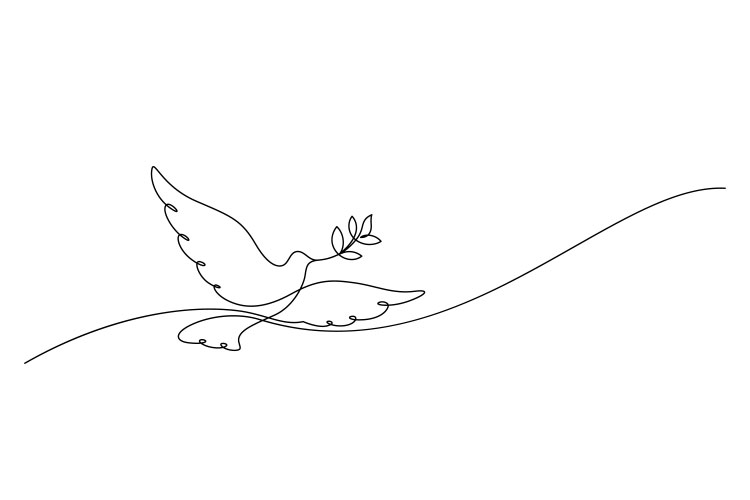
自分のことがどんなに受け入れがたかったとしても、もし、「今のあなたのままでいいんだ、そのままで十分価値があるんだ、そんなあなたが大切なんだ」と純粋に思ってくれる誰かと出会うことができたとしたら、私たちはとても救われ、今の自分を確かな出発点にして、意欲と希望を持って自分の人生を着実に生きていく、大きなきっかけとなるでしょう。
さらには、自分のかえがえのなさを大切にできるようになると、他の人のありようも尊重でき、他者や社会と調和して生きていけるようになるでしょう。 ロジャーズは、そんな姿を「十分に機能している人」として理想的なカウンセリングの最終目標、つまり、私たちの幸せのありようとみなしたのです。
カウンセラーの基本的態度
このように、あるがままの自分を無条件に受け止め、肯定してくれる誰かとの出会いは、とても大きな力を持ちます。
ロジャーズは、それこそが、カウンセラーが何を置いてもすべきことで、人生のままならなさに苦しむクライエントの今のありように寄り添い、共感し、無条件に尊重するといった姿勢やかかわりこそが、悩み苦しむ人が回復し、自らの力で幸せの道を歩んでいくようになるための、最も効果的な方法だと考えのです。
他方、助言や指導などは、学習された「価値の条件」に苦しみ、自己疎外に悩む人たちには、その人が本来の自分らしく自分の人生を生きていけるようになる可能性を、かえって損ねてしまいます。
だからこそ、カウンセリングの基本は、まさに「傾聴」、「共感」、「受容」であり、それは今や、ロジャーズ派を超えて、広くカウンセラーが身につけておくべき基本とされています。
仮に皆さんがカウンセリングを受けて、助言やアドバイスが少ないと思ったらとしたら、これまでお話ししたようなな考え方、つまり、できるだけ価値の条件なしに、あなたの体験や想いに寄り添い、それを肯定的に受け入れることこそが、あなたを支えるのに役に立つといったスタンスによるものです。
ただし、実際は、必ずしも助言や指導がない方がいいとは限らないところもありますので、もし、そのことに疑問や不満を感じたり、あるいは、回数を重ねてもあまり楽になる感じがしないなと思ったら、そのことを率直にカウンセラーに尋ねてみてください。
本当にあなたのことを尊重している人であれば、そんなあなたの迷いや不満にも虚心に耳を傾けてくれ、共に考えようとしてくれるはずです。
「共感」や「寄り添い」による癒しと回復
実は、そのような「共感」や「寄り添い」による癒しは、専門家カウンセラーに限らずとも、誰にも可能なことです。
私たちには基本的に、悩む苦しむ相手に寄り添いたいという生来的な志向性が備わっています。物心つく前の乳児が、心苦しむ母親の頭をなでてあげたりするのも珍しいことではありません。その志向性がうまく発揮されると、誰もが「癒し手」になり得ます。
ならばどうして、専門家カウンセラーが必要なのでしょうか?
それは、私たちは、ときにそうあることは可能でも、常に相手に寄り添い、共感して、受け入れ続けるということは、とても難しいからです。
特に、家族などの身近な関係は、身近なだけにさまざまな感情が沸き起こり、相手を受け入れようとすることで、逆にこじれた関係になってしまうことも多いのです。
だから、そうならないようにトレーニングを受けたカウンセラーによるカウンセリングが大切ということになります。
でも、専門家カウンセラーといえども、常に共感的、受容的でいられるとは限りません。例えば、社会的な「価値付け」に影響されて、知らず知らずのうちに、相手を判断・評価してしまったり、カウンセラー自身も、いろいろあった来し方を、自分なりのやり方で対処したり、乗り越えてきたりしているので、そんな「価値づけ」が影響して、クライエントに好き嫌いの感情を持ったりしてしまうこともあります。
ただし、そのような想いを持ってしまうカウンセラーが、良くないカウンセラーということではありません。
信頼できるカウンセラー
信頼できるカウンセラーとは、自分自身の不十分さや弱みを受け入れながら、日々の営みの中で「十分に機能する人間」に近づこうとしており、自分とは生まれも育ちも違う相手の生き方に共感することの限界を知っていながらも、なおかつ、相手に寄り添い、共感的関係を「築こうとすること」の癒しの力を信じている人です。
もし皆さんがカウンセリングを続けても、自分を大切にしたい感じがなかなか起きてこず、むしろ、かえって自分を責めたり、さいなんでしまうことが続いてしまうような場合は、そのカウンセラーとは相性が悪いと思ってください。
カウンセラーの専門的な知識や語りに納得できることよりも、カウンセリングを受けて、自分自身を責めたり、さいなんだりする気持ちが軽くなり、今のあるがままの自分を大切に、そこから歩みを進める意欲や安らぎが沸いてくるかどうかが、カウンセリングの良し悪しを判断する大きな目安です。
自分で自分を大切にする 自分で自分を癒す
注意すべきこととして、そのような誰かからの「共感」や「癒し」を期待しすぎると、逆に自分の苦しみが増してしまうということが、往々にしてあります。
苦しいときに身近な人(やカウンセラー)に「共感」してもらうこと、「受容」してもらうことを求めすぎるあまり、それが十分にできない相手に、失望や不満や怒りが湧いてしまうことがあるのです。
それはときに、相手への「恨みつらみ(逆恨み)」となり、そうなると、本来、頼れる相手との間で、とても難しい関係になってしまいます。
親子や夫婦などの家族のこじれた関係の背後で、とてもよく起こっていることです。
(ちなみに、夫婦や家族、親子などの関係の拗れに対しては、個人へのカウンセリングの専門性だけでは十分に対応できません。家族療法・家族カウンセリングのトレーニングを受け、かつ、信頼できる専門家をなんとか、見つけてください。)
このHPに、「家族療法、家族カウンセリングの考え方」のわかりやすい説明も今後アップする予定です。参考までに、少し専門的なお話になりますが、以下の記事を読んでみてください。
自分で自分を思いやる
どんなに優しい相手でも神さまではありませんから、「共感」や「癒し」を他の人に求めるのは限界があります。だから、できれば、他の人を直接頼らなくとも、苦しんでいる自分のことを自分自身で「思いやる」、自分で「癒せる」ようになりたいのです。
それがある程度はできないと、いつも誰か頼みになり、なかなか心の安らぎや幸せには近づけません。
ここでは、そのための一つの方法を紹介してみようと思います。
「コンパッションセラピー」(参考文献は「セルフ・コンパッションのやさしい実践ワークブック / T.ディズモンド著」など)と呼ばれる、自分で自分をケアする考え方を参考に、アレンジしたものです。
まず、自分の呼吸に注意を向け、空気が流れ込んできて、流れ出ていくときの身体の感覚に注意を集めることで、心を「今この瞬間」に置きます。そして、その注意を今度は呼吸から、身体の感覚、あるいは、心の中に沸いてくる感情や考えに広げていきます。(この一連の所作は、「マインドフルネス」と呼ばれ、このHPの『マインドフルネスの考え方』のところで、もう少し詳しく説明しています)
人生があまりうまくいっていないときには、嫌な感情や考えや、体のある部分の緊張や不快感がとても強くなり、すぐにでも自分の中から追い払いたくなります。
そのとき、すぐにそうせず、それらがどんな表情や迫り方や正体をしているかを観察するようにします。それらの「声」や「訴え」を聴くと言ってもいいかもしれません。
そして、それらの「声」や「訴え」に、「怒り」とか「淋しさ」とか「不安」とか「脅え」とか「悲しみ」とか、近い名前をつけてみてください。自分の中の苦しみの部分を俯瞰的に見てあげられ、追い払うというよりも、それらを労わる雰囲気が出てくるでしょう。
ちなみに、自分の体の感覚や感じは、自分の「考え」よりも確かであることが多く、それをうまくつかめるようになると、今の自分の状況や苦しみがより良く理解できるようになります。
ロジャーズの影響を強く受けたジェンドリンという人は、「フォーカシング」という方法を提唱し、そのような身体の感じをうまくつかむことを通じて、自己理解や自己受容、自己成長が促がされるとして、幸せな人生に近づく道筋を示しています。
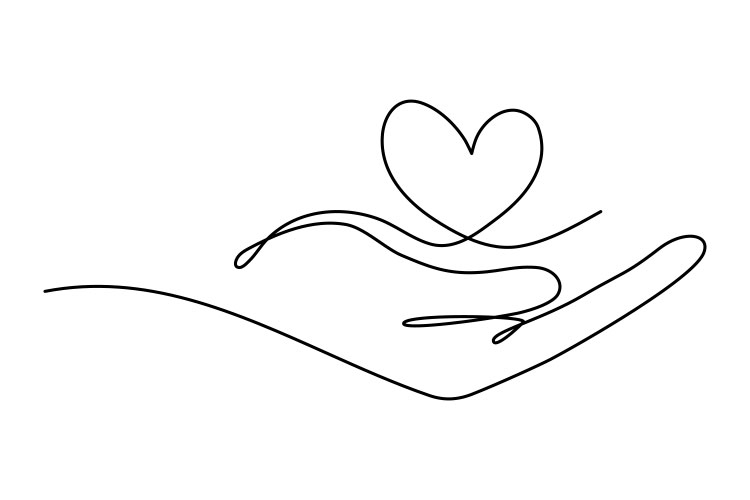
心の中の不快な「面々」も、自分の大切な「分身」
話を戻しますが、心の中の不快で嫌な「面々」も、自分の大切な「一部」であり「分身」です。何かしらの意味があって、理由があってそこにいるのです。
ですから、その「面々」を追い払おうとせず、受け入れてあげ、ケアしてあげることが、すなわち自分を思いやること、大切にすることにほかなりません。
その際、その「面々」をあたかも、泣いていたり、脅えていたり、怒っていたり、悲しんでいたりする小さい子どもとして見てあげると、受け入れてケアしてあげるイメージを持ちやすいでしょう。
例えば、「寂しくて不安なんだね。(大丈夫、そばに一緒にいてあげる)」、 「怒ってるんだね。(そうだよね、わかるわかる)」、「悲しいね。(うんうん、よしよし。)」などのように、寄り添ってあげられるできるでしょうし、「(その子が)安らかでありますよう」、「幸せでありますよう」と祈ってあげることもできるでしょう。
自分を大切にする練習を重ねる
たとえ、親との関係に恵まれなかったとしても、私たちは自分をケアし、自分を癒せるようになれるのです。小さい頃の体験に恵まれず、苦しい人生を送ってきた人ほど、それがとても難しく、到底できないように錯覚してしまいがちです。
でも、だからこそ、ほかでもない自分が自分のことを大切にしてあげる、幸せにするという覚悟を持って、あきらめずに繰り返して練習して、それを習慣にしてください。
練習を繰り返すことによって、自分を思いやり大切にする脳内の回路が成長し、幸福感が高まるというエビデンスだってあります。
自分を自分で大切にする一つの具体的方法をお伝えしましたが、ほかにも方法はいろいろあります。例えば、『認知行動療法(カウンセリング)の考え方』のところで紹介しますが、「言葉の力を借りる」というのもその一つです。
誰にでも自分に合った、自分のやりやすい方法がいくつか見つかるはずです。
自分の人生が苦しければ苦しいほど、あきらめずにいろいろ試して、人生を乗り切るためのアイテムを増やしていきましょう。
自分を大切にするための具体的な行動こそが、幸せへの一番の近道です。それが習慣となれば、自分のことはもちろん、周囲の人のありようも大切に想えるようになっていくでしょう。